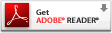はじめに-職業行為基準の意義(1)
規律委員会委員長 山本 高稔
1.証券アナリストを取巻く環境の変化と役割の多様化
1990年代初期にバブルが崩壊した後は、「失われた20年」を経て「失われた30年」ともいわれる中、日本株に対する投資魅力は大幅に失われていった。世界全体の時価総額に占める日本株の比率は、バブル絶頂期の1980年代末時点では3分の1を超えており、一時期、アメリカの株式市場をも上回る規模であった。ところが、その後は、日本の株式市場は長期的な低迷期に陥り、近時の株価上昇を加味しても、世界の株式市場における構成比は1割を大きく下回っている。
世界の株式市場における日本市場の相対的な比率が縮小したことは事実であるが、日本の株式市場の社会的な役割が小さくなった訳ではない。国民年金と厚生年金の年金積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)等の公的年金の運用では、政策資産配分における株式の比率(中心値)を50%とする動きが見られ、そのうち半分の25%は国内株式へ配分する方針を採用している。また、2012年に発足した第2次安倍内閣のもとでは、成長戦略の一環として国内企業に対するコーポレートガバナンスを強化する政策が採用され、2014年には「スチュワードシップ・コード」、2015年には「コーポレートガバナンス・コード」が相次いで導入され、ガバナンス強化を通じた日本企業の「稼ぐ力」の強化、そして中長期的に企業価値の増加を促す政策が実施されている。また、2014年に公表された「伊藤レポート」(脚注1)では、資金の供給者から最終的な需要者に至るまでの資金の流れを「インベストメント・チェーン(investment chain)」と称して、関係者がそれぞれの立場で最善の努力を行うことが、日本の企業や経済の健全な成長にとって不可欠であると指摘している。
その後、コーポレートガバナンス改革をより実質的なものへと深化させていくことを目的として、2017年および2020年に「スチュワードシップ・コード」が、2018年および2021年には「コーポレートガバナンス・コード」が改訂され、それとともに機関投資家と企業の対話において重点的な議論が期待される事項を取りまとめた「投資家と企業の対話ガイドライン」が策定・改訂されている。また、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループの提言(2022年6月)を踏まえて、2023年3月期から有価証券報告書にサステナビリティ情報の「記載欄」が新設されたほか、人的資本・多様性やコーポレートガバナンスに関する開示が拡充されている。
2023年12月には、政府が「資産運用立国実現プラン」を公表し、個人の安定的な資産形成を促進し、国内投資を活性化させ、「成長と分配の好循環」を実現していくことを目的とした包括的な政策が示された。その中では、資産運用業・アセットオーナーシップ改革が、資産所得倍増プラン及びコーポレートガバナンス改革と並ぶ3本柱とされており、企業年金等と資産運用会社の役割発揮と運用対象の多様化、スチュワードシップ活動の実質化などが求められている。
証券アナリストは、企業の本源的価値の分析・評価を通じて、主に投資家が投資判断するうえでの情報提供を行う役割を担っているが、以上のような環境の変化を受けて、証券アナリストに対する期待がますます高まっている。短期的な値上がり見込みの高い株式を推奨するだけでなく、中長期的な視点から日本企業の成長性や収益性を分析・評価するためにも、証券アナリストの発信する情報の重要性が高まっているといえる。
このように、証券アナリストに対するニーズは多様化しており、様々な視点から情報提供を行うことが期待されている。2016年9月、日本証券業協会はアナリストによる発行会社への取材や、アナリスト・レポート以外の手段による情報伝達のあり方などについての考え方のガイドラインを制定した。また、2018年4月には企業がアナリストなどに未公表の重要情報を伝えた際に、直ちに公表を求める「フェア・ディスクロージャー・ルール」と呼ばれる金融商品取引法の規制も導入された。情報発信の担い手である証券アナリストにとって、こうした環境変化の中で、多様化するニーズに応え、その役割を遂行することは容易ではないが、こうしたことへの挑戦が新しいアナリストの世界を開拓し、また日本の株式市場の再活性化への原動力の一つになるものと確信している。
(脚注1) 正式名称は、「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~ 」プロジェクト「最終報告書」。経済産業省から2014年8月に公表された。一橋大学の伊藤邦雄教授が座長を務めたことから「伊藤レポート」と呼ばれており、その後の「コーポレートガバナンス・コード」のベースとなった。なお、2017年10月に「伊藤レポート2.0」、2022年8月に「伊藤レポート3.0」が公表されている。