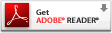証券アナリストジャーナル賞
論文審査の経緯ならびに結果について(論文審査委員会報告)
証券アナリストジャーナル編集委員会
委員長 加藤 康之
1.論文審査の経緯
今次の証券アナリストジャーナル賞の対象は、2024年4月号から2025年3月号に掲載された論文およびノート、計71編であった。編集委員会では、これらについて、(1)独創性、(2)論理の展開力、(3)実務への応用性、の三つの審査基準に着目して、以下の3段階にわたる審査を経て、受賞作の選定を行った。なお、編集委員およびモニターが執筆した論文(共同執筆を含む)は、慣例により本賞の対象外としている。
第1段階: 編集委員(30名)とモニター(5名)が書面により1~2編の論文を受賞候補として推薦(2025年3月に実施)。
第2段階: 4月11日に予備審査委員会(編集委員長、小委員長、研究者委員および実務家委員の計9名で構成)を開催、第1段階において3名以上の委員・モニターから推薦のあった10編の論文につき精査し、受賞論文を予備選定。
第3段階: 5月9日に全編集委員による審査委員会を開催、予備審査委員会において絞り込まれた受賞候補論文を中心に最終審議を行い、受賞作を決定。
2.選考結果
今回の選定では、以下の4編が僅差で最終候補に残った(掲載順)。
- 2024年5月号「四半期報告利益を用いた利益調整行動の分析」縄田寛希氏
- 2024年7月号「日本の製造業における事業撤退・新規参入と社外取締役の導入」守屋亮佑氏
- 2024年10月号「四半期決算発表に対する市場反応の実証分析―企業の情報環境によって変化する利益情報の有用性―」屋嘉比潔氏・松本紗矢子氏
- 2025年2月号「決算発表日の集中度がアナリスト予想の適時性に与える影響」縄田寛希氏
いずれも力作であったが、最終的に次の2編を受賞論文として選定した(掲載順)。
- 2024年5月号「四半期報告利益を用いた利益調整行動の分析」縄田寛希氏
- 2024年7月号「日本の製造業における事業撤退・新規参入と社外取締役の導入」守屋亮佑氏
双方とも、タイムリーで読者層の関心が高く分かりやすい論文であったことが審査委員の評価を高くした。なお、屋嘉比・松本論文(2024年10月号)、縄田論文(2025年2月号)も大変興味深いテーマを扱った実証分析であり、読み応えも十分であった。
選考結果(1) 縄田寛希(2024年5月号)
「四半期報告利益を用いた利益調整行動の分析」![]() (1,593KB)
(1,593KB)
選定理由
縄田論文は、四半期財務データを活用して企業による第4四半期の利益調整行動を検証している。四半期開示については、その有用性について様々な議論がありタイムリーなテーマであった。筆者の貢献は、多くの日本企業が年次利益の赤字回避のため第4四半期に利益調整を行っているという仮説を立て、その実証を試みたことである。分析対象は金融以外の上場企業で、17年間の四半期利益と四半期累計利益データである。そして、四つの各四半期におけるこれらデータの分布を多角的に検証している。その結果、第4四半期累計利益の黒字割合は第3四半期に比べて有意に高く、第4四半期累計利益の分布は利益ゼロ付近で第3四半期に比べて不連続性が顕著であり、そして、第4四半期利益の分散は有意に大きいが累計利益はそうでないことが示された。さらに追加の分析として、利益調整が会計処理的なものか、あるいは、支出削減などの実体的調整なのかを検証し、会計的なものが有意であるという結果を示した。これらの実証結果を総合的に判断し、多くの企業で第3四半期累計赤字から第4四半期累計黒字に転換していること、そして、それが企業の裁量によるものであることを示していると結論している。そのロジックは丁寧に説明されている。本稿の結果は、企業の利益調整に関する裁量行動を明らかにすると同時に、四半期データの有用性を示すものとして意義がある。なお、筆者も指摘しているが、利益の目標ベンチマークや企業の属性による相違など残されたテーマも少なくない。今後の研究に期待したい。
受賞者コメント

縄田 寛希 氏
この度は、栄誉ある「証券アナリストジャーナル賞」を賜り、誠に光栄に存じます。ジャーナル編集委員の皆様、匿名レフェリーの方々、選考に携わってくださった皆様、そして日頃よりご指導・ご支援を賜っている皆様に、心より御礼申し上げます。
ご選出いただいた論文「四半期報告利益を用いた利益調整行動の分析」は、修士論文の一部を再構成したものです。本論文では、四半期ごとに開示される利益情報に着目し、経営者による利益調整行動の過程を検証しました。検証結果は、年次利益の赤字を回避するため、経営者が第4四半期に利益調整を行っているという説明と整合的なものでした。これは、四半期ごとに企業に決算開示を求める四半期財務報告制度が、経営者の行動をモニタリングする上で有用であることを示唆しています。
執筆に当たり重視したのは、検証結果を視覚的に分かりやすく示すことです。第3四半期から第4四半期にかけて、四半期累計利益における利益分布の不連続が形成されるプロセスを図示したことは、複雑な統計分析以上に説得力を持つと考えています。このアプローチの基盤となったのは、Burgstahler and Dichev[1997]の研究であり、その「論より証拠」と言わんばかりの視覚的かつ直感的な手法は、現在でも多くの研究者や大学院生に影響を与え続けています。
研究を開始した当時、四半期財務報告のコストとベネフィットに関する議論が活発化していました。とくに、四半期決算短信そのものの廃止や提出書類の簡略化などが検討されており、こうした社会的関心が研究に着手する大きな動機となりました。結果として、四半期報告制度の廃止という時流の変化と重なり、本論文がタイムリーなテーマとして評価いただけたことは、幸運にほかなりません。今回の受賞を大きな励みとし、今後も研究活動に真摯に取り組んでまいります。
選考結果(2) 守屋亮佑(2024年7月)
「日本の製造業における事業撤退・新規参入と社外取締役の導入」![]() (2,942KB)
(2,942KB)
選定理由
守屋論文は、日本の製造業における事業の撤退や新規参入における社外取締役導入の影響について実証的に分析したものである。コーポレートガバナンスの重要性が高まる中、タイムリーで読者の関心が高いテーマである。筆者の貢献は、ガバナンスの効かない企業では経営者が「平穏な生活」を望み、既存事業からの撤退や新規参入に躊躇する可能性があるという仮説を立て、その実証を試みたことである。分析では、撤退と新規参入をダミー変数で表し、これを社外取締役比率などの変数で説明しており、分かりやすい分析モデルになっている。分析の結果、社外取締役比率が高いほど、企業は既存事業からの撤退を行いやすく、また、新しい業界への新規参入を行いやすいことが示された。さらに、社外取締役の影響は、事業の集中度が低いほど撤退に対して、そして投資機会が小さいほど新規参入に対して、それぞれ強くなることも明らかにされており興味深い。コーポレートガバナンス・コードの導入以降、企業は社外取締役の増員に舵を切り、その数は顕著に増加した。一方、そのガバナンスの効果に対して疑問を呈する指摘もある。本稿は、社外取締役がガバナンスの向上に一定の効果をもたらすことを示し、重要な知見を提供している。なお、分析の一部には、統計的解釈やモデル設計に慎重な解釈が求められる結果も含まれており、今後の研究においてさらなる検証の余地を残している。また、収益性や企業価値に対する社外取締役の影響や他のガバナンス指標の効果など、さらなる研究にも期待したい。
受賞者コメント

守屋 亮佑 氏
この度は、栄えある証券アナリストジャーナル賞をいただき、誠にありがとうございます。審査いただきました匿名のレフェリー2名と編集委員長、また論文執筆に多大な助言をいただきました一橋大学の安田行宏教授に心から御礼申し上げます。
社外取締役は、その導入効果に実務・研究両面で議論があるテーマではないかと思います。社外取締役導入はコーポレートガバナンス改革の取り組みの一つであり、効果があるとする論拠の一つには、経営者が企業価値向上ではなく個人の利益を追求してしまうエージェンシー問題という考え方があります。日本企業の場合、経営者が困難な意思決定を避けるという平穏な生活追求(quiet life)仮説が当てはまることをIkeda et al. [2018]が指摘しています。本論文では、企業の撤退・新規参入と社外取締役比率の関係性をテーマに平穏な生活追求(quiet life)仮説を踏まえた検証を行い、エージェンシー問題が果たしてあるのか、なぜエージェンシー問題が生まれるのかを検証いたしました。
分析の結果、社外取締役比率は企業の撤退や新規参入と有意に正の相関があること、また、売上高が特定のセグメントに集中していない企業では社外取締役比率と撤退との相関が強くなり、トービンのqが低く投資機会が大きくない企業では社外取締役比率と新規参入との相関が強くなることが確認できました。社外取締役という外部の視点を取り入れたことで撤退や新規参入が増えた要因として、Rajan et al. [2000]を参考に社内の調和を優先するような経営者の内向き思考と、事業部のような組織単位での保身的な行動という二つの要因を論文の中で指摘しました。
エージェンシー問題とそれを解消するためのコーポレートガバナンスの取り組みについて実務・研究両面でさらに理解が深まること、企業が困難な意思決定を避けてしまう原因が分かることで、投資家や企業自身が今後その原因に対処できるようになり、日本における企業価値向上につながることを期待しています。