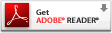証券アナリストジャーナル賞
論文審査の経緯ならびに結果について(論文審査委員会報告)
証券アナリストジャーナル編集委員会
委員長 川北 英隆
論文審査の経緯
今次の証券アナリストジャーナル賞の大賞は、2021年4月号から2022年3月号に掲載された論文およびノート、計60編であった。編集委員会では、これらについて、(1)独創性、(2)論理の展開力、(3)業務への応用性、の三つの審査基準に着目して、以下の3段階にわたる審査を経て、受賞作の選定を行った。なお、編集委員およびモニターが執筆した論文(共同執筆を含む)は、慣例により本賞の対象外としている。
第1段階:編集委員(32名)とモニター(8名)が書面により1~2編の論文を受賞候補として推薦(2022年3月に実施)。
第2段階:4月8日に予備審査委員会(編集委員長、小委員長、学者委員の敬7名で構成)を開催、第1段階において3名以上の委員・モニターから推薦のあった9編の論文につき精査し、受賞論文を予備選定。
第3段階:5月13日に全編集委員による審査委員会を開催、予備審査委員会において絞り込まれた受賞候補論文を中心に最終審議を行い、受賞作を決定。
選考結果(1) 臼井健人(2021年11月号)
「投資家の含み損益と低ボラティリティ・アノマリー」![]() (926KB)
(926KB)
選定理由
臼井健人氏の論文が扱うのは、日本の株式市場における低ボラティリティ・アノマリー、すなわちボラティリティの低い銘柄ほど期待リターンが高い傾向に関する実証分析である。このアノマリーが生じる背景として投資家の心理バイアスを指摘している。
本論文のベースは、2005年のGrinblattとHanの手法を日本市場での個別企業に適用することにより、投資家の平均的な購入価格と含み損益を計算することにある。この計算に用いているのは1977年から2020年までの週次データである。
最初に、この含み損益を用いて日本市場の特徴を観察し、平均的な投資家として含み損を抱えた銘柄が多いことと、含み損のある銘柄と比較して含み益のある銘柄が積極的に売買されていることを示している。その上で投資家が、含み益のある銘柄群に対してはリスク回避的に、含み損のある銘柄群に対してはリスク愛好的になるとの分析結果を得ている。言い換えれば、含み損のある場合、リスクとしてのボラティリティとリターンの間に負の関係(アノマリー)があると結論する。
本論文の貢献は投資家の含み損益をキーワードとして、売買行動、ボラティリティ、リターンの相互の関係を分析することにより、日本市場におけるアノマリーの存在を明らかにしたことにある。実務的にも大変有益だと考えられる。
今後について、筆者自身も指摘しているが、データの制約があるものの、多様な投資家を想定しつつ損益の推定方法を工夫し、投資行動の特徴をより詳細に分析することに期待したい。
選考結果(2) 地主純子(2022年1月号)
「決算短信は他の企業情報と比較して重要な情報か」![]() (976KB)
(976KB)
選定理由
地主純子氏の論文のテーマは、日本の証券取引所が義務づけている決算短信が投資家にとって重要な情報源であるかどうかを実証的に分析することにある。
この点を他の五つの情報、すなわち企業による業績予想、証券会社アナリストの売りもしくは買い推奨、有価証券報告書、適時開示・任意開示書類、金融商品取引法による開示書類と比較している。実際の比較分析には米国の先行研究が用いた方法から四つを用い、情報の公表が分析対象企業の株価の異常リターン(市場全体の株価変動に関係しないリターン)をどの程度説明できるのかを求めることで、それを情報の重要性の指標としている。分析データとしては2002年7月1日から19年6月30日までのものを用いている。
以上の分析から、決算短信が投資家に対して定期的に新たな情報を提供しており、開示頻度と情報量の観点から重要であるとの結果を得ている。また時系列的にみると、決算短信の重要性が増していることも示されている。
本論文の意義は、四半期ごとの情報開示に対して批判的な声が生じている中、他の公開情報と比較することにより、決算短信が定期的に提供している情報の重要性を実証的に示したことにある。
今後のテーマとして、筆者自身が述べているように、決算短信の中の情報として重要なものは何なのか、その絞り込みに期待したい。このことは、企業として最低限公表すべき情報の特定と、任意で提供する情報の優先順位づけに役立つだろう。