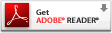図書紹介
データで広がる日本ワインの世界:ワインエコノミクス入門
原田喜美枝 著(日本評論社)
本書は、ワイン好きな経済学者が日本のワイン産業の成長のために著したワインエコノミクスの入門書である。本書では多様な論点が取り上げられているので、その中からいくつかを紹介する。
まず、日本で飲まれているワインは大きく3つに分類される。輸入ワイン、日本ワイン、国産ワインである。輸入ワインは文字通りであり、日本ワインは日本のブドウを発酵させてできたものである。一方、国産ワインとは、主に輸入された濃縮ブドウジュースを使って国内で、新たに酵母や砂糖、香料を加えて発酵させたアルコール飲料であり、国際的にはワインとはみなされないものである。
世界的なワイン消費動向を見ると、欧州で伝統的にワインを造ってきたオールドワールド(フランス、イタリア、スペインなど)では、1950年代をピークに消費量は大きく落ち込んでいる。ニューワールド(オーストラリア、ニュージーランド、アメリカなど)では、2010年頃までは増加してきたが、近年は伸び悩んでいる。日本では、清酒、ビールの消費が大きく落ち込んでおり、ワインは比較的安定している。
日本のワイン消費量は全体として横這いの中で、ワイナリー数は長野や北海道を中心に急激に増えている。新規参入ワイナリーは主に日本ワインを製造しているが、零細・小規模なところが多く、経営は苦しい。そこで、著者はワイナリーの経営分析とクラウドファンディングや政府系金融機関による資金調達(農業経営基盤強化資金<通称スーパーL>)について解説している。
また、地理的表示保護制度(GI)は馴染みがないが、日本産のスパークリングワインをシャンパンと呼ぶことができないのは、この取り決めによる。ニューワールドのワインには、欧州の産地名を使用しないとの協定も結ばれている。
このほか、ワインの貿易や統計、税金についても解説されており、とかく高級で趣向的な飲み物と思われがちなワインについて、その実態を知ることができる貴重な書である。
著者の原田喜美枝氏は、中央大学商学部教授。日本ソムリエ協会ワインエキスパート。
目次
第1部 消費・市場関連のワインエコノミクス
第1章 消費と生産の関係
第2章 日本のワイン産業
第3章 ワインの地理的表示
第4章 資金調達とワイン投資
第2部 貿易関連のワインエコノミクス
第5章 ワインの貿易
第6章 ワインの統計
第7章 ワインの税金