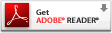図書紹介
60代からの資産「使い切り」法 -今ある資産の寿命を延ばす賢い「取り崩し」の技術-
野尻哲史 著 (日本経済新聞出版)
著者は、退職世代が今ある資産を有効に使っていくために必要なのは、資産の運用を続けながら取り崩して、資産寿命を伸ばしていく包括的なアプローチ、すなわち「資産活用」の技術であると主張している。
まずその前提として、現役世代(勤労収入>生活費)と退職世代(勤労収入<生活費)の違いから説き起こしている。現役世代では、勤労収入=生活費+貯蓄・資産形成となる一方、退職世代では、生活費=勤労収入+年金収入+資産収入となる。
現役世代へのアドバイスは、まず貯蓄・資産形成を決めて生活費を抑えることから始めることが一般的である。退職世代には、①生活費を引き下げること、②勤労収入を少しでも多く長く受け取れるようにすること、③年金収入を少しでも多く受給できるようにすること、④資産収入を長く・多く確保できるように資産運用し、そして取り崩し方を考えることだと言う。そして、生活費、勤労、年金、資産運用については、多くの知見やノウハウが流布しているが、資産の取り崩し方にはほとんど言及されておらず、そこに重点を置いたのが本書の特徴となっている。
日本の金融ビジネスは、顧客の資産を増やすことが顧客サービスだとしか考えていないため、退職金をハイリスク・ハイリターンの仕組債で運用するようアドバイスするなど誤ったセールスが行われ問題となっている。著者は、現役世代の資産形成期(積み立てながら運用)を山登りに、退職世代の資産活用(前期:運用を継続しながら取り崩し、後期:運用は停止して取り崩しのみ)を山下りに例えて説明している。
特に資産活用前期の資産運用を継続しながらの取り崩し方については、かつてのように預貯金での金利収入がある程度見込めた団塊世代では、金融資産を全て預貯金にして、毎月例えば10万円ずつ定額で引き出していくアドバイスは分かりやすく問題もなかったという。しかし、ゼロ金利は解除されたとはいえ依然低金利の時代には、収益率に変動がある有価証券で運用しながら取り崩していくことを考えなければならない。その場合には、「収益率配列のリスク」があるため、定額ではなく定率での引き出しが適切であると強調している。
収益率配列のリスク(sequence of returns risk)とは聞き慣れない言葉だが、定額引き出しを前提として、一定期間を平均した運用収益率は同じケースであっても、毎年の収益率が期間前半の方が後半より高い場合とその逆の場合を比較すると、前者の方が一定期間後の資産残高が大きくなり、後者とかなり格差がつくことである。しかし、事前には先行きの収益率の配列がどうなるかは分からないため、収益率の配列の違いによる資産残高の振れを抑えるには、毎年定額の引き出しでなく、毎年の資産残高に対して定率で引き出していくことが有効であると数値例を使って丁寧に解説している。
また、こうした考え方を踏まえて、100歳まで資産寿命が持つようにするための逆算の資産準備なども提示している。
著者の野尻哲史氏は、元フィデリティ退職・投資教育研究所所長で、定年退職後に合同会社フィンウェル研究所を設立し、現在代表を務める。
目次
序 章 資産形成を終えた人に第1章 「資産活用」世代の実態
第2章 リタイアメント・インカムとは?
第3章 「毎月10万円の引き出し」はなぜキケンなのか
第4章 引き出しは「率」で考える
第5章 保有する資産全体のなかで取り崩しを考える
第6章 資産活用層は新NISAをどう使う?
第7章 生活スタイルと資産活用
第8章 資産活用層の社会貢献